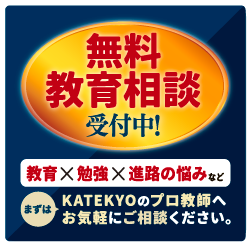TOPICS from KATEKYO
70年ぶりの転換点:「ち」が「ti」から「chi」へ

2024年7月14日、文化審議会は日本語ローマ字表記の70年ぶりの大改定となる答申案を決定しました。ここで注目されたのが、仮名「ち」を従来の「ti」から国際的に浸透している「chi」へ変更するという提言です。単なる文字列の置換えにとどまらず、言語が社会とどう折り合い、国際コミュニケーションを円滑化していくのかを問い直す歴史的な一歩と言えるでしょう。
二つの表記法が歩んだ道のり
訓令式とヘボン式――二つのローマ字表記法は、それぞれ異なる理念の下で発展してきました。1937年に制定された訓令式は50音図の規則性を重視し、「ti」「si」といった形で配列の整合性を保つものでした。一方、幕末に宣教師 J.C.ヘボンが考案したヘボン式は英語話者が直感的に読める音韻重視の表記で、「chi」「shi」などが特徴です。
制度上は訓令式が「正式」ながら、現実にはパスポートや駅名標など生活インフラの多くがヘボン式で表記されています。制度と実態のねじれが長年にわたり放置されてきたことが、今回の見直しを後押しした背景にあります。
言語は生きている
言語は社会を映す鏡であり、固定されたルールの上にあっても、時代の要請に応じて姿を変えます。英語圏に浸透した「judo」「matcha」「tsunami」といった語のローマ字は、いずれもヘボン式に準拠しています。グローバル化の加速度を考えると、国際的慣用と歩調を合わせた表記の採用は、合理的で実用的な選択だと言えるでしょう。
教育現場への影響と課題
今回の提言は、学校教育に少なからぬインパクトを与えます。70年間訓令式で学んできた世代と、ヘボン式ベースで学ぶ世代が混在する過渡期が生まれるからです。しかし、「規則性重視」から「実用性重視」への転換は、ICTや英語学習との親和性を高め、ローマ字をより使いやすいツールへと昇華させる契機にもなるでしょう。
また、長音や拗音など細部の表記ルールも整理が進めば、学習者にとって一貫性の高い体系が構築される見込みです。
変化への配慮と継承
答申案は訓令式の完全否定ではなく、長年培われた規則性と文化的蓄積を尊重しています。個人・団体が従来表記を継続利用できる余地を残し、急激な断絶を避けるソフトランディング型の改革です。継承と革新のバランスをとる姿勢は、他分野の制度改定にも示唆を与えるでしょう。
未来への架け橋
70年ぶりの転換は、単なる綴りの変更にとどまらず、言語と社会、教育と国際化の接点を再設計する試みです。伝統を尊重しつつ変化を受け入れる今回の決定は、言語政策の理想的プロセスの一つといえるかもしれません。日本語の国際的プレゼンスを高め、より多くの学習者に開かれた言語へ――その第一歩が静かに踏み出されました。
言語は時代とともに育ちます。「ち」を「chi」と書く未来は、私たちの発信力を一層強くするでしょう。今後の授業や日常生活で新表記に触れたときこそ、変化を学びの機会と捉え、自分の言葉で世界とつながる力を磨いてみてください。
参照リンク
- ローマ字表記の混在を改善へ 「ち」は「ti」?「chi」?(掲載日:2024年5月14日、2025年7月16日 アクセス)
- ローマ字のつづり方に関する今期の審議のまとめ(案)(掲載日:2024年3月、2025年7月16日 アクセス)
※リンク先は変更される場合があります。最新情報は公式サイトでご確認ください。
◎『KATEKYO学院・山形県家庭教師協会』では、英語・国語の両面からローマ字指導の最新カリキュラムを提供します。お気軽にご相談ください。
担当:プロ教師 近江直樹
各校の「TOPICS」はこちら