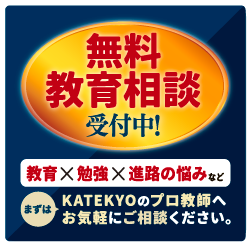TOPICS from KATEKYO
デジタル教育と紙の教科書のバランス~フィンランドの事例から学ぶ教育の未来
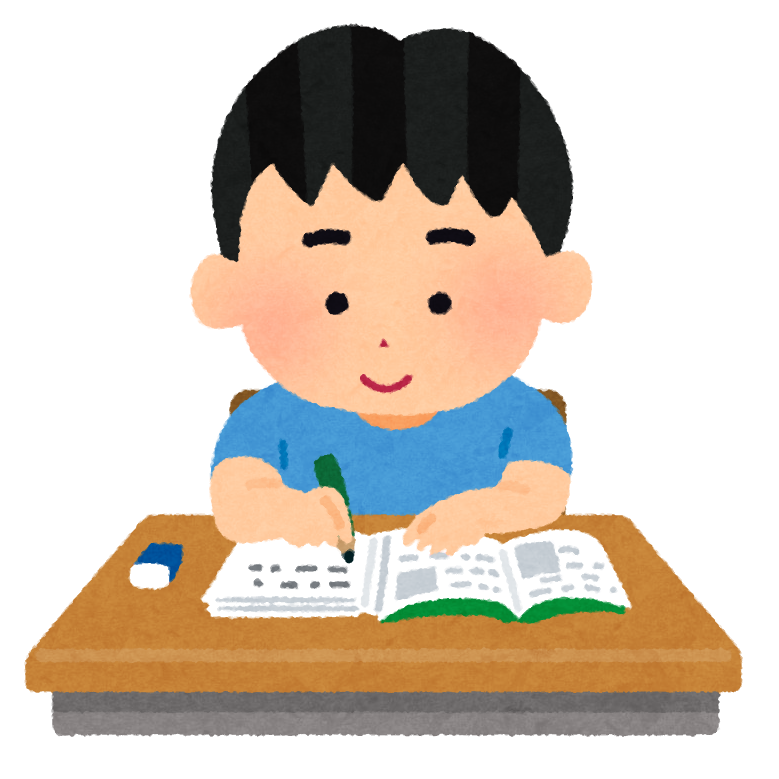
〇教育のデジタル化と紙の回帰
教育先進国として知られるフィンランドで興味深い現象が起きています。積極的にデジタル技術を教育に導入してきた同国で、成績低下や児童・生徒の心身の不調が目立つようになり、紙の教科書が再び注目されるようになったのです。この動きは、世界中の教育関係者に重要な問いかけをしています—デジタル技術と従来の教育手法のバランスをどのように取ればいいのでしょうか。
〇世界的なデジタル教育の推進
21世紀に入り、多くの国々が教育現場にデジタル技術を積極的に取り入れてきました。OECD(経済協力開発機構)の「教育とスキルの未来」プロジェクトでもデジタルリテラシーの大切さが強調され、特にコロナ禍を経て、オンライン学習プラットフォームの導入が世界中で加速しました。
フィンランドは特に早い段階からデジタル教育に力を入れ、一人一台のデバイス提供など、教育のデジタル化において先駆的な役割を果たしてきました。その新しい取り組みは、21世紀型スキルを育てるモデルケースとして、日本を含む多くの国々に影響を与えてきました。
〇デジタル教育の二面性
デジタル技術の導入は、教育に多くの良い点をもたらしました
・インタラクティブな教材による学習体験の広がり
・一人ひとりに合わせた学習の実現
・情報に簡単にアクセスできる
・先生と子どもたちのコミュニケーションがスムーズに
・みんなで学び合う新しい可能性
しかし、フィンランドの例が教えてくれるように、デジタル化には思わぬ課題も出てきています。
1. 学力への影響
・PISA(国際学習到達度調査)の結果で、かつての上位常連国から順位を落としている傾向があります
・特に読解力や長い文章を理解する力の低下が目立っています
・デジタル機器の使用で集中力が散りやすく、じっくり考え続けることが難しくなっているようです
2. 心身の健康問題
・長時間の画面使用で視力が低下したり、姿勢が悪くなったりしています
・ブルーライトを浴びすぎることで睡眠に問題が出ています
・デジタル機器の使いすぎでストレスや不安が増えているケースも見られます
3. 頭の使い方への影響
・紙の教材と比べると、デジタル教材では深く読み取ることや情報を記憶に残すのが難しいという研究結果もあります
・手で書くノートが減ったことで、記憶への定着に影響が出ているかもしれません
4. デジタル格差の拡大
・家庭によってデジタル機器の使い方やスキルに差があり、教育の格差が広がる心配があります
・技術を使える環境や周りのサポートに差があると、学ぶ機会に不公平が生まれるかもしれません
〇紙の教科書復活の脳科学的な意味
フィンランドで進められている紙の教科書への回帰には、脳の働きに関する科学的な根拠があります。
1. 情報処理と記憶の定着
・紙の本を読むと、画面で読むよりも情報の位置関係がつかみやすく記憶に残りやすいという研究結果があります
・紙の手触りやページをめくる動作が、脳の中で情報を整理するのを助けている可能性があります
2. 集中力と深い学びの促進
・デジタル機器がない環境では、通知やいろんな作業に気が散ることが少なくなります
・紙の教科書だと自然と読むスピードが遅くなり、内容をより深く理解できるという研究もあります
・線を引いたりメモを書いたりと、積極的に読む行動が自然と増え、主体的に学ぶ姿勢が育ちます
3. 健康面での配慮
・ブルーライトを浴びる時間が減り、睡眠の質が良くなります
・姿勢や目への負担が軽くなります
・画面を見る時間全体が適切になり、心のストレスも減ります
〇バランスを大切にした教育の進め方
フィンランドの例から学べる最も大切なことは、「デジタルか紙か」という二者択一ではなく、それぞれの良いところを活かしたバランスの取れた方法の大切さです。
デジタルツールの良いところ
・情報を素早く集められる
・見て分かりやすい
・みんなで協力しやすい
・一人ひとりに合わせた学習
紙の教材の良いところ
・じっくり読み深められる
・長い文章も理解しやすい
・記憶に残りやすい
・集中力が続きやすい
勉強する内容や目的に合わせて、デジタルと紙を使い分ける「ブレンデッド・ラーニング」という考え方が大切です
さらに、子どもの年齢や発達に合わせた使い分けも重要なポイントです。
・低学年の子どもには実物や紙の教材を中心にして、感覚を通した学びを大切にする
・年齢が上がるにつれて少しずつデジタルスキルを学ぶ機会を増やしていく
・常に学習の目標に合った手段を選ぶ柔軟さを持つ
〇日本の教育へのヒント
日本でもGIGAスクール構想により1人1台端末の環境が整いつつある中、フィンランドの経験から学べることはたくさんあります。
1. 教育の目標をはっきりさせたICT活用
・「デジタル機器を使うこと」自体が目的にならないよう気をつける
・なぜ、どんな場面でデジタルツールを使うのかを常に考える
2. 子どもの年齢に合わせた使い分け
・低学年では紙の教科書や実物を使った勉強を中心にする
・高学年になるにつれて、しっかり考える力を育てながらデジタルツールを上手に活用する範囲を広げる
3. 先生方の学びとサポート
・デジタル技術を効果的に活用するための先生向けの研修を充実させる
・先生自身がデジタルと従来の教育方法のバランスを取る判断力を身につける
4. デジタル格差をなくす
・家庭環境によるデジタル機器の使いやすさの差をなくすためのサポートを考える
・学校での機器の使用時間やルールについての指針を整える
5. 科学的な証拠に基づいた教育の実践
・脳科学の発見を取り入れた教材選びと教え方の工夫
・定期的に効果を確かめ、柔軟に方針を調整する仕組みづくり
まとめ
フィンランドで紙の教科書が見直されている動きは、単に「デジタルをやめる」ということではなく、より子どもたちの学びに効果的な方法を「最適化する」試みと考えるべきでしょう。教育でのデジタル技術は強力な道具ですが、万能薬ではないことをフィンランドの例は教えてくれています。
デジタル技術を使う目的は、あくまでも子どもたちの学びを助け、その可能性を広げることです。技術を使うこと自体が目的にならないよう、常に教育の本当の意味—考える力、判断する力、表現する力、そして学ぶ意欲を育てること—に立ち返ることが大切です。
フィンランドが示す新しい方向性は、デジタルと紙のバランスを取りながら、子どもたちの特性や発達段階、学ぶ内容に合わせて最適な学習環境を作っていく道筋を示しています。日本を含む世界中の教育に関わる人たちは、この貴重な経験から学び、より効果的な教育の形を探していくことが求められています。
–
–
–
–
◎KATEKYO学院では、皆さん(小学生、中学生、高校生)の夢を実現するためのサポートを、プロ教師による完全個別指導で行っています。これから中学校や高校に進学を考えている皆さん、一緒に夢の実現への最短ルートを探してみませんか?
—-
—–
担当)プロ教師 近江直樹
—-
—-
参照:URLをクリック↓
デジタル導入の「教育先進国」で成績低下や心身の不調が顕在化…フィンランド、紙の教科書復活「歓迎」(読売新聞オンライン) – Yahoo!ニュース
各校の「TOPICS」はこちら