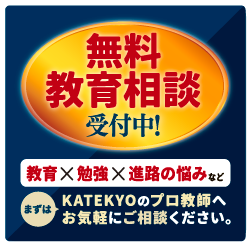TOPICS from KATEKYO
子どもの読書離れ ~データが語る現実と、家庭でできる読書習慣づくり~

通勤電車や学校帰りのバスで本を読む子どもを、最近見かけましたか?今、多くの子どもたちがスマートフォンに夢中です。これは単なる印象ではなく、調査データでも「読書離れ」が明確に進行していることがわかっています。本を読む子が減る中で、家庭ができる工夫とは何でしょうか。
今回わかったこと:半数以上が「読書0分」
2024年のベネッセ教育総合研究所の調査によると、1日の読書時間が「0分」の子どもは52.7%に達しました。9年前の34.3%から大幅増です。30人のクラスに換算すると、約16人が月に1冊も本を読んでいない計算になります。
また全国学校図書館協議会の調査では、「1か月に1冊も本を読まない」割合が小学生8.5%、中学生23.4%、そして高校生では48.3%と、学年が上がるほど増えています。
読書がもたらす3つの力
1. 深く考える力
短い情報を次々と読むSNSとは違い、本は集中して読まなければ理解できません。一冊を読み通す過程で集中力・持続力・論理的思考力が育ちます。読書時間が長い子ほど、語彙力・読解力が高い傾向も明らかです。
2. 想像力と共感力
物語を通じて、異なる時代や文化、他人の気持ちを疑似体験できます。登場人物の心情を理解する過程で、共感力や思いやりの心が自然と育まれます。
3. 自分と向き合う時間
スマートフォンが「常に刺激を与える存在」である一方、読書は静かに自分の内面と向き合う行為です。この時間が、思索力や自己理解を深める貴重な機会となります。
子どもが本を読まなくなった理由
主な要因はスマートフォンの普及です。スマホは短時間で多くの刺激を与えますが、本は「集中して読み進める忍耐力」を求めます。その違いが、読書離れを加速させています。
さらに、「親の読書習慣」が子どもの読書量に影響するという調査もあります。親が本を読む姿を見せるだけで、子どもが本を手に取る確率が高まるのです。
家庭でできる5つの工夫
- 10分読書タイムを設定:夕食後など決まった時間に家族全員で読書。
- 本棚をリビングに置く:いつでも手に取れる環境を整える。
- 親も本を読む姿を見せる:「読んで」と言うより行動で示す。
- 本選びは子どもに任せる:マンガ・図鑑でもOK。興味を優先。
- 読み聞かせを継続:小学校高学年まで続けると読書習慣が定着。
家庭から始まる小さな変化の事例
中学2年生の健太さん(仮名)は、3か月前に家族で始めた「夜の10分読書」で変化がありました。最初は気乗りしなかったものの、今では寝る前に自分から本を開くようになり、休日には図書館に行きたいと言うようになったそうです。
お母さんは「スマホの時間がゼロになったわけではないけれど、本を読む時間ができたことで親子の会話が増えた」と話します。
デジタルと読書の共存
スマートフォンを完全に排除するのではなく、読書に活かすこともできます。電子書籍なら通学中にも読めますし、オーディオブックなら「耳で本を聴く」ことも可能です。読書記録アプリで友人と感想を共有するのも、現代らしい読書の形です。
まとめ:1冊の本から未来を変える
読書離れは確かに深刻ですが、解決不能ではありません。家庭での小さな工夫が、子どもの心を大きく変えます。
「今日10分だけ本を読む」。それだけで十分です。スマホを置いて家族で過ごす静かな時間が、子どもたちの未来に新しい扉を開くでしょう。
📚 参考リンク
- ベネッセ教育総合研究所「子どもの生活と学びに関する親子調査2024」(アクセス日:2025-10-28)
- 全国学校図書館協議会「第69回学校読書調査」(アクセス日:2025-10-28)
- KATEKYOトピック関連記事(アクセス日:2025-10-28)
※リンク先は変更される場合があります。最新情報は公式サイトでご確認ください。
◎『KATEKYO学院・山形県家庭教師協会』では、家庭での学習習慣づくりや読書推進をサポート。小学生から高校生まで、読解力・表現力を育てる指導を行っています。無料相談も随時受付中です。
担当:プロ教師 近江直樹
各校の「TOPICS」はこちら